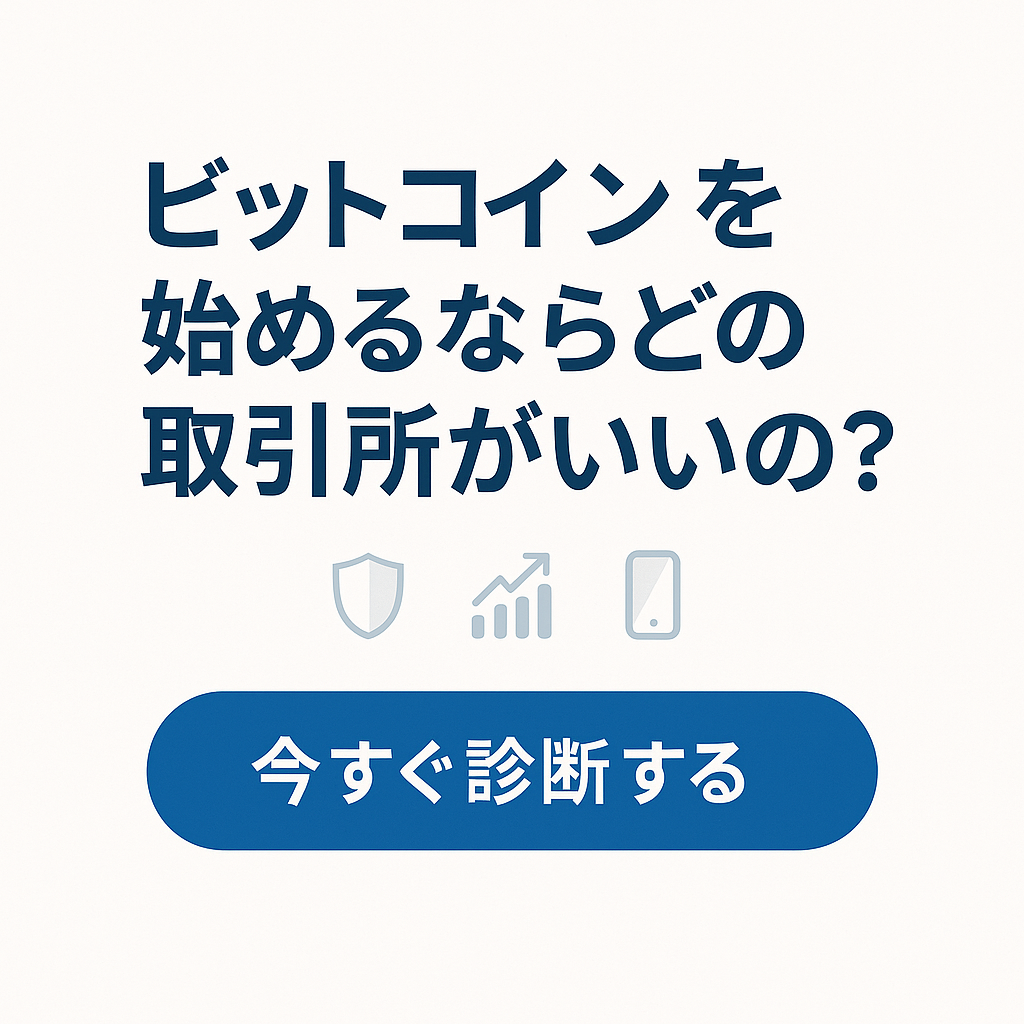目次
レイ・ダリオ氏とは?世界的投資家のプロフィールと影響力
要約: 世界最大級のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」の創業者で、「全天候型ポートフォリオ」を提唱した現代を代表する伝説的投資家です。
経歴と実績
レイ・ダリオ(Ray Dalio)氏は、現代金融界で最も影響力のある投資家の一人です。1949年生まれ、2025年現在76歳。ヘッジファンド業界の「レジェンド」として、以下のような実績を持ちます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 創業ファンド | ブリッジウォーター・アソシエイツ(1975年設立) |
| 運用資産 | 現在は約900億ドル規模。2020年には約1,500億ドルのピークに到達し、世界最大級のヘッジファンドに。 |
| 推定個人資産 | 約150億ドル前後(Forbes等の長者番付推計) |
| 代表著書 | 『PRINCIPLES(プリンシプルズ)』などの世界的ベストセラー |
全天候型ポートフォリオの提唱者
ダリオ氏がブリッジウォーター内で1990年代半ばに開発した「オールウェザー・ポートフォリオ(全天候型ポートフォリオ)」は、投資戦略の金字塔として知られています。全天候型ポートフォリオの代表的構成例
株式:30%
米国長期国債:40%
米国中期国債:15%
金:7.5%
コモディティ:7.5%
※ブリッジウォーターが運用する機関投資家向けポートフォリオとは細部は異なりますが、個人投資家向けに広く紹介されている「目安」として、上記のような配分が知られています。
戦略の核心
- あらゆる経済環境(成長×インフレの4象限)で安定したリターンを目指す
- 特定の「シナリオ当て」ではなく、リスク分散で下落耐性を高める
- 「何が起きるか」ではなく「何が起きても致命傷を負わない」設計
市場への影響力
ダリオ氏の発言は、世界中の投資家や政策当局に大きな影響を与えます。
- マクロ経済分析:長期債務サイクル理論など独自フレームワークを提唱
- 政策提言:各国政府・中央銀行に対し講演・助言
- 投資家教育:書籍・インタビュー・SNSで投資哲学を公開
ビットコイン保有の公表:総資産1%配分が持つ重大な意味
要約: 2025年11月、ダリオ氏は「自分のポートフォリオの約1%をビットコインで長年保有している」と明言しました。同時に、ビットコインへの「慎重な楽観」と、量子コンピュータリスクへの強い懸念も示しています。
発言の詳細
2025年11月20日前後、CNBCなど複数メディアのインタビューで、ダリオ氏は次のような趣旨の発言をしています。
「私は長い間、ポートフォリオのごく一部、約1%をビットコインに配分してきました。それは変わっていません」
実際、Yahoo Financeなどの報道でも、「small percentage(小さな割合)」=全資産の約1%程度がビットコインであると本人が述べたと伝えられています。
同時に、ビットコインが将来「準備通貨」になる可能性については否定的で、その理由として追跡可能性・量子コンピュータリスク・規制リスクを挙げています。
1%配分の重要性
一見小さく見える「1%」ですが、その意味は非常に大きいです。
金額規模の目安
- ダリオ氏の推定総資産:約150億ドル前後
- その1%:約1.5億ドル(約225億円相当)
この規模は、一般的な個人投資家から見れば「機関投資家クラス」のポジションであり、「完全に無視しているわけではない」ことをはっきり示す数字です。
「小さいがゼロではない」配分の哲学
報道では、ダリオ氏のスタンスは一貫して次のように整理できます。
- ビットコインには構造的な弱点や不確実性がある
- しかし、完全に排除するほど無価値とも見ていない
- したがって、ポートフォリオのごく一部にとどめるのが妥当
長期保有の意義
ダリオ氏は、「長い間(for a long time)保有している」とも述べています。
これは以下を示唆します。
- 一時的な投機ではない:短期の売買ではなく、長期の構造変化を観察するためのポジション
- ポートフォリオの固定枠に近い:状況を見ながら多少調整はあっても、「ゼロにしない」枠として扱っている
- 市場と技術の推移を見極めるための「席」:完全に席を外すのではなく、一定のエクスポージャーを残しておく姿勢
量子コンピュータリスクとは?ビットコインに迫る新たな脅威
要約: ダリオ氏がビットコインに対して最も懸念しているのが、「量子コンピュータによる暗号解読リスク」です。短期的には脅威ではないものの、長期的にはビットコインの根幹を揺るがしかねないテーマとして、議論が活発化しています。
ダリオ氏の警告内容
ダリオ氏は、ビットコインを準備通貨と見なさない主な理由として、次の点を挙げています。
- 取引が追跡可能(traceable)であること
- 将来、量子コンピュータによってハッキングされ得ること
- そのため「主要国の準備通貨になるのは難しい」
つまり、ビットコインを完全否定しているわけではありませんが、「国家レベルの基軸通貨としては脆弱だ」という評価です。
量子コンピュータとは
量子コンピュータは、従来のコンピュータとは異なる「量子力学」に基づいて動作する次世代コンピュータです。
| 項目 | 従来型コンピュータ | 量子コンピュータ |
|---|---|---|
| 基本単位 | ビット(0 or 1) | 量子ビット(0と1の重ね合わせ) |
| 計算方式 | 基本的に直列処理 | 理論的には大規模な並列計算 |
| 得意分野 | 日常的な計算・業務処理 | 特定の問題(最適化・因数分解など)の超高速解法 |
暗号学的に重要なのは、「大きな素因数分解」や「離散対数問題」を高速に解ける可能性がある点です。これが現在の公開鍵暗号の多くを脅かします。
ビットコインの暗号技術への脅威
ビットコインは、主に次の2つの暗号技術に依存しています。
- SHA-256ハッシュ関数(PoWマイニングなどに使用)
- ECDSA(楕円曲線デジタル署名)(秘密鍵・アドレスの保護)
現在のコンピュータでは、これらを実用的な時間で破ることは不可能とされていますが、理論上は量子コンピュータ+ショアのアルゴリズムにより、ECDSA署名などが短時間で解読される可能性が指摘されています。(Barron's)
- 従来コンピュータ:実質「宇宙の寿命を超える」時間が必要
- 理論上の強力な量子コンピュータ:十分な論理量子ビット数と誤り訂正があれば、現実的な時間で解読可能
専門家の見解:いつ現実化するのか?
量子リスクが「本当に問題になる時期」について、専門家の見解は割れています。
悲観的な見方(数年〜10年以内にリスクが顕在化)
ベンチャー投資家のChamath Palihapitiya氏は、Googleの量子チップ「Willow」などの進展を踏まえ、
- 「今後2〜5年程度で、量子コンピュータがビットコインの暗号を脅かすレベルに到達する可能性」を警告。
といった趣旨の発言をしています。
楽観的な見方(20〜40年は安全)
一方で、ビットコイン草創期から暗号技術に関わってきた**アダム・バック氏(Blockstream CEO)**は、最近のインタビューで、
- 「ビットコインが量子コンピュータから現実的な脅威にさらされるのは、少なくとも今後20〜40年先」だとコメントし、
- 現在SNSなどで騒がれている「数年以内にビットコイン終了」という見方を過度に悲観的だと批判しています。
共通認識
- 「今すぐに破られるわけではないが、長期的には無視できない」
- NIST(米国標準技術研究所)などがポスト量子暗号(PQC)の標準化を進めており、ビットコイン側にも「備える時間はある」というのが、比較的コンセンサスに近い見方です。
Google量子チップ「Willow」と市場の動揺
2024年末〜2025年にかけて、Googleが発表した量子チップ「Willow」は、既存のスーパーコンピュータを大きく上回る処理性能を実証し、一部メディアや投資家の間で「暗号解読が目前なのでは?」という懸念を呼びました。
これをきっかけに、
- ビットコインは過去に10万ドル台を付けた水準から、直近では約9.1万ドル→8.6万ドル台まで急落し、
- 短時間で約2億ドル超のロングポジションが清算されたと報じられています。
ただし、Google Quantum AIの責任者自身が、
「Willowは現在のRSAや楕円曲線暗号を破れるような性能には全く達していない。実際に暗号を解読するには、何百万という論理量子ビットと長期安定動作が必要」
と明言しており、「現時点でビットコインの暗号が危険な段階にあるわけではない」ことも強調されています。
ビットコインコミュニティの対応策
量子リスクに対し、ビットコイン側でも次のような議論・準備が進んでいます。
- 量子耐性アルゴリズムへの移行検討
- NISTが標準化を進めるポスト量子暗号(PQC)の採用検討
- 署名方式を段階的に切り替えるソフトフォーク案 など
- 「20〜40年の猶予」を生かした設計
- 現在のウォレット・アドレス設計の見直し
- 古い公開鍵が露出しているアドレスからの資産移行キャンペーン
結論として、短期的にビットコインが量子コンピュータで破られる可能性は低いものの、長期投資家はこのリスクを知っておく必要がある、というのが現状です。
ダリオ氏のポートフォリオ戦略:なぜビットコインは1%なのか
要約: ダリオ氏の「ビットコイン1%配分」は、新興資産への戦略的エクスポージャーと、徹底的なリスク管理のバランスを体現しています。
全天候型ポートフォリオの進化
従来、ダリオ氏が提唱してきた「全天候型ポートフォリオ」には、ビットコインのような暗号資産は含まれていませんでした。
しかし近年の発言では、
- 「債務の増大や通貨価値の希薄化に備えるには、金や(少量の)ビットコインのようなハードマネー資産が重要」
- 「ポートフォリオの10〜15%程度を金やビットコインなどの代替資産に配分するのは合理的」
といった趣旨のコメントを繰り返しており、従来の株・債券中心の分散投資に「デジタル時代のハードマネー」を部分的に組み込む方向に進化していることが伺えます。
一方で、自身のポートフォリオではビットコイン部分は1%程度に抑えていると明かしており、
- 「資産全体の中では小さいが、完全にゼロではない」
- 「金など他の実物資産の比重がはるかに大きい」
というバランスを取っています。
なぜ1%なのか?5つの理由
1. 新興資産クラスへの慎重なアプローチ
ビットコインは登場からまだ16年程度の非常に新しい資産クラスであり、数十年スパンでの実績が不足しています。
- 通貨としての位置付けも確立途上
- 規制環境も国ごとに大きく異なる
- 技術リスク(量子コンピュータなど)も残る
こうした「不確実性」を踏まえ、少額から様子を見るというスタンスは合理的と言えます。
2. 「オプション性」としての位置づけ
1%という小さな配分でも、ビットコインが大きく成長した場合の恩恵は無視できません。
例として:
- 現在価格:9万ドル付近と仮定
- 10年後に50万ドルに到達した場合(あくまで仮定)
- 1% → 約5〜6%相当まで拡大
- ポートフォリオ全体のリターンに有意なインパクト
ダリオ氏は、こうした「大きく上振れしたときのオプション」を安価に買っているとも解釈できます。
3. リスク・リターンの最適化
全天候型ポートフォリオの本質は、「リスク調整後リターンを最大化」することです。
- ビットコインがゼロになっても損失は1%に限定
- 一方で、価格が数倍〜数十倍になれば全体リターンを押し上げる
- 残り99%は株式・債券・金などで安定性を確保
「失ってもいい範囲で上振れを狙う」という、極めてプロらしいリスク管理です。
4. 金との比較における相対的評価
ダリオ氏は以前から金に対しては非常に好意的で、
- 「長期的な価値保存手段」
- 「通貨価値の希薄化へのヘッジ」
として、10〜15%程度の配分を推奨してきました。
これに対し、ビットコインは、
- 歴史が短く、
- 規制・技術リスクも大きく、
- 中央銀行が保有しているわけでもない
ことから、金よりもかなり小さい配分(1%)にとどめていると考えられます。
5. 量子リスクへの懸念
前述の通り、ダリオ氏は量子コンピュータによる長期的な暗号解読リスクを極めて重く見ており、
- 「長期の準備通貨としては不適切」
- 「技術が進化するほど攻撃面も進化する」
といった趣旨の発言をしています。
こうした「長期的な構造リスク」を考慮すれば、1%という慎重な配分は合理的です。
機関投資家の動向:ビットコイン採用が進む一方で慎重論も
要約: 2024年のビットコイン現物ETF承認以降、機関投資家の参入は着実に進んでいますが、ダリオ氏のような慎重派も健在で、市場は「強気派」と「警戒派」に二極化しています。
ビットコイン現物ETF以降の変化
2024年1月、米SECが複数のビットコイン現物ETFを承認したことで、
- BlackRock(IBIT)
- Fidelity(FBTC)
などの大型ETFが立ち上がり、短期間で数百億ドル規模の資産を集めました。
これにより、
- 従来は参入が難しかった保守的な機関投資家(年金・基金など)も、
- 「ETFを通じてビットコインに間接的に投資しやすくなった」
という環境が整いつつあります。
慎重派と強気派のコントラスト
慎重派の代表:レイ・ダリオ氏
- 全ポートフォリオの約1%のみビットコイン
- 量子リスクや規制リスクを強く意識
- 「参加はするが、深くは踏み込まない」スタンス(
極端な強気派:マイケル・セイラー氏(MicroStrategy)
- 企業として数十万BTC規模の保有を公表
- 自らも強烈なビットコイン推進者として知られる
- 「ビットコインは究極の資産」という立場を取る
否定派:ウォーレン・バフェット氏
- 「ビットコインは何も生み出さない資産」として、一貫して投資を否定
- 保有比率は0%
このように、機関・著名投資家のスタンスは大きく分かれています。
ダリオ氏の1%配分は、「全面否定でも全面肯定でもない、中庸の立場」として非常に参考になります。
個人投資家への示唆:ダリオ氏から学ぶリスク管理の実践
要約: ダリオ氏の「ビットコイン1%」戦略は、個人投資家にとっても、新興資産への賢明なアプローチモデルになります。
ダリオ氏の戦略から学ぶ5つの教訓
1. ポートフォリオ全体の視点で考える
- ビットコイン単体の上下ではなく、「全資産のうち何%か」で考える
- ダリオ氏は1%だが、個人投資家も1〜5%程度を目安に検討するのが現実的
例:投資可能資産が1,000万円なら、
- ビットコイン:10〜50万円
- 残り:株式・債券・金・現金などで分散
2. 長期保有を前提とする
- 「長い間持っている」と語るように、短期の値動きにはあまり振り回されていない
- 個人投資家も、最低5年〜10年の長期保有を前提にすることで、
- 日々の急騰・急落に振り回されにくくなります。
3. リスクを理解してから投資する
ビットコインには、株式・債券とは異なる固有のリスクがあります。
- 規制リスク
- 技術リスク(ハッキング・量子リスクなど)
- カストディ(保管方法)の問題
「よく分からないものには大金を入れない」という姿勢は、どの資産にも共通する鉄則です。
4. 新興資産には控えめな配分を
リスク許容度別の目安:
| リスク許容度 | ビットコイン配分目安 | 想定投資家 |
|---|---|---|
| 保守的 | 0〜1% | 退職後・資産防衛重視 |
| 中立的 | 1〜3% | 30〜50代・バランス志向 |
| 積極的 | 3〜5% | 20〜40代・成長重視 |
| 投機的 | 5〜10%以上 | 暗号資産の知識が深い人向け |
10%を超える配分は、「投機的」と考えた方が安全です。
5. 分散投資の徹底
ダリオ氏の全天候型戦略の根幹は「徹底した分散」です。
例:30代・積極型の個人投資家ポートフォリオ案
国内株式:30%
海外株式:30%
債券:20%
金:10%
ビットコイン:3%
現金:7%
このように、ビットコインを「ポートフォリオの一部」として組み込むのが、より現実的でリスク管理にも適ったアプローチです。
日本の主要仮想通貨取引所
BitTrade(ビットトレード)
特徴
- 豊富な暗号資産銘柄を取り扱い(46銘柄前後)
- 高度なセキュリティシステム
- 初心者から上級者まで対応のUI/UX
主要手数料
- 売買手数料:販売所スプレッド、取引所 無料
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:330円
- 送金手数料:銘柄により異なる
最小購入額:販売所500円、取引所0.00001BTCかつ2円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
向いているユーザー:多様な銘柄への分散投資を検討している方
SBI VCトレード
特徴
- SBIグループの信頼性と実績
- 業界最低水準の手数料体系
- 充実したレンディング/ステーキング/積立
主要手数料
- 売買手数料:無料(現物)
- 入出金手数料:無料
- 送金手数料:無料(ネットワーク手数料相当は別途)
取扱銘柄:36銘柄 最小購入額:1円〜(取引所)/販売所は銘柄により異なる
積立サービス:毎月500円から レンディング:年率は募集時条件により変動
セキュリティ:金融庁認可業者の高度なセキュリティ
向いているユーザー:手数料を最小限に抑えたい初心者〜中級者
Coincheck(コインチェック)
特徴
- 国内トップクラスの暗号資産取引所
- 初心者にも分かりやすいシンプルな操作性
- NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」運営
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所は銘柄ごとに設定(BTC/ETHは無料対象)
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:407円
- 送金手数料(BTC):0.0005 BTC
取扱銘柄:35銘柄 最小購入額:500円
積立サービス:月1万円から(対応銘柄は拡充傾向)
特別サービス:Coincheck NFT、IEO実施経験
向いているユーザー:暗号資産初心者、NFTに興味がある方
bitbank(ビットバンク)
特徴
- 全暗号資産取引量 国内トップクラスの実績(媒体報道)
- 高度な取引ツールとチャート機能
- Maker手数料マイナス(報酬システム)
主要手数料
- 売買手数料:Maker -0.02%/Taker 0.12%
- 入金手数料:無料(クイック入金等は条件あり)
- 出金手数料:550円/770円(3万円以上)
- 送金手数料(BTC):0.0006 BTC
取扱銘柄:国内最多クラス(40銘柄以上) 最小購入額:0.0001 BTC
積立サービス:定期購入あり(最小100円〜、販売所)
セキュリティ:コールドウォレット、マルチシグ対応
特殊機能:リアルタイム入金、高度な注文機能
向いているユーザー:取引量の多いアクティブトレーダー、上級者
OKJ(オーケージェー)
特徴
- 世界大手OK Groupの日本法人による運営
- 業界トップクラスの狭いスプレッド
- 高利回りFlash Dealsやステーキングサービス
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所 Maker 0.07%/Taker 0.14%(基準) ※取引量で優遇あり
- 入金手数料:無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料(日本円):100万円未満 400円/100万〜1,000万円未満 770円/1,000万円以上 1,320円
- 送金手数料:銘柄により異なる(例:IOSTは低コスト)
取扱銘柄:50銘柄(2025年11月時点、MEME上場反映) 最小購入額:500円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
独自サービス:Flash Deals(高利回りの実績)、マルチチェーン対応
向いているユーザー:スプレッド重視、多様な銘柄に分散投資、レンディング/ステーキングに興味がある方
bitFlyer(ビットフライヤー)
特徴
- ビットコイン取引量9年連続 国内トップクラス
- 創業以来ハッキング被害ゼロの高度なセキュリティ
- 1円から取引可能な初心者に優しい設計
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所0.01~0.15%(取引量により変動)
- 入金手数料:住信SBIネット銀行 無料、その他銀行 330円(クイック入金)
- 出金手数料:三井住友銀行 220円/440円、その他 550円/770円
- 送金手数料(BTC):0.0004 BTC(XRP・MONA・XLM等は無料)
取扱銘柄:39銘柄(現物) 最小購入額:1円
積立サービス:対応 レバレッジ取引:bitFlyer Lightningで最大2倍(BTC、ETH対応)
セキュリティ:マルチシグ、コールドウォレット、2段階認証
特別サービス:bitFlyer クレカ(利用額の0.5~1.0%をBTC還元)、ビットコインをもらう、IEO実績
向いているユーザー:少額から始めたい初心者、取引量の多いアクティブトレーダー、レバレッジ取引に興味がある方
よくある質問(FAQ)
Q1. レイ・ダリオ氏がビットコインを1%しか保有しないのはなぜですか?
A. 新興資産としてのリスクと、量子コンピュータなど長期的な不確実性を重く見ているからです。
- 歴史が短い
- 規制・技術の変化が激しい
- 準備通貨になりにくい構造的な要因がある
といった点から、「完全にゼロにはしないが、あくまで少額」というスタンスを取っています。
Q2. 量子コンピュータは本当にビットコインの脅威になりますか?
A. 長期的には脅威となり得ますが、専門家の多くは「少なくとも20〜40年の猶予がある」と見ています。一方で、2〜5年以内のリスクを警告する声もあり、見解は分かれています。
- 悲観的:Chamath氏などが「2〜5年以内にリスクが顕在化し得る」と警告
- 楽観的:アダム・バック氏などが「20〜40年は現実的な脅威はない」と反論
共通しているのは、
- 「今すぐに暗号が破られる段階ではない」
- しかし「将来に備えてポスト量子暗号への移行準備は必要」
という点です。
Q3. ダリオ氏の「全天候型ポートフォリオ」にビットコインを組み込むべきですか?
A. リスク許容度次第ですが、組み込むとしても全体の1〜3%程度にとどめるのが現実的です。
従来の構成:
株式:30%
長期国債:40%
中期国債:15%
金:7.5%
コモディティ:7.5%
ビットコインを組み込む一例:
株式:29%
長期国債:38%
中期国債:15%
金:7%
コモディティ:7%
ビットコイン:2%
現金:2%
この程度であれば、
- ポートフォリオ全体の安定性を大きく損なわず
- ビットコインの上振れを適度に取り込むことができます。
Q4. ビットコインと金、どちらに投資すべきですか?
A. ダリオ氏の考え方を参考にすると、金を主軸に、ビットコインは「補完的に少額」という位置付けが妥当です。
| 項目 | 金 | ビットコイン |
|---|---|---|
| 歴史 | 数千年 | 約16年 |
| ボラティリティ | 中程度 | 非常に高い |
| 供給 | 年1〜2%増加 | 2,100万枚で固定 |
| 中央銀行保有 | 大量に保有 | ほぼゼロ |
| 推奨配分(例) | 10〜15% | 1〜3% |
結論:
- 「守り:金」
- 「攻め:ビットコイン(少額)」
という組み合わせが現実的です。
Q5. ダリオ氏の発言は、ビットコイン投資の判断にどの程度影響させるべきですか?
A. 非常に参考になる一方、「唯一の正解」として盲信すべきではありません。
活用の仕方としては、
- リスク管理の模範例として学ぶ
- 1%という慎重な配分
- 新興資産を「オプション」として位置付ける発想
- 他の著名投資家の意見と比較する
- 極端な強気派・否定派と見比べることで、自分の立ち位置を客観視できる
- 最終的には自分の状況で判断する
- 年齢・資産規模・収入・家族構成・リスク許容度
- 投資目的(老後資金か、成長投資か、短期投機か)
ダリオ氏の結論(1%)が、そのままあなたの正解になるとは限りません。
しかし、「新興資産への慎重な関わり方」という意味では極めて優れた参考例になります。
まとめ:レイ・ダリオ氏の警鐘が示す「賢いビットコイン投資」
最後に、この記事のポイントを整理します。
- ダリオ氏はビットコインを完全否定していない
- 総資産の約1%を長期保有している事実は、ビットコインの可能性を一定程度認めている証拠。
- しかし、量子リスクや規制リスクを強く意識している
- 将来の量子コンピュータや追跡可能性から、「準備通貨にはなりにくい」と評価。
- 新興資産には「小さな配分で参加する」という戦略
- 全資産の1〜3%程度であれば、ゼロになっても致命傷にならない
- 大きく上昇した場合の上振れも取りに行ける
- 量子リスクは「今すぐの脅威」ではないが、長期的には無視できない
- 悲観派は2〜5年、楽観派は20〜40年という幅広い見積り
- ポスト量子暗号やプロトコル更新への備えが重要
- 個人投資家にとっての実践知
- ポートフォリオ全体の1〜5%の範囲で検討
- 長期保有を前提とし、短期の上下に振り回されない
- 金や株・債券とのバランスを重視する
「完全否定でも全面肯定でもなく、慎重に参加する」
これこそが、ダリオ氏から学べるビットコインとの賢い付き合い方と言えるでしょう。
参考資料・出典
- Ray Dalio関連
- Yahoo Finance「Ray Dalio Still Owns Bitcoin, but Says Traceability and Quantum Computers Limit Its Role」
- PANews「Ray Dalio: about 1% of my portfolio is in Bitcoin」
- The Crypto Basic「Billionaire Ray Dalio Shares Why Bitcoin Cannot Be a Reserve Currency for Major Countries」
- 量子コンピュータ・量子リスク
- CoinMarketCap Academy「Bitcoin Faces No Quantum Threat for Next 20-40 Years, Says Adam Back」
- Ainvest / ZyCrypto「Quantum countdown: 5-year alarm vs 20-year defense buffers」
- The Verge「Google says its breakthrough quantum chip can't break modern cryptography」
- 投資戦略・ポートフォリオ
- Diamond Online「オールウェザー・ポートフォリオ解説記事」
※本記事は2025年11月21日時点の情報に基づいており、その後の新しい発言・価格変動・技術進展は反映されていない可能性があります。投資判断は必ずご自身の責任と判断で行ってください。