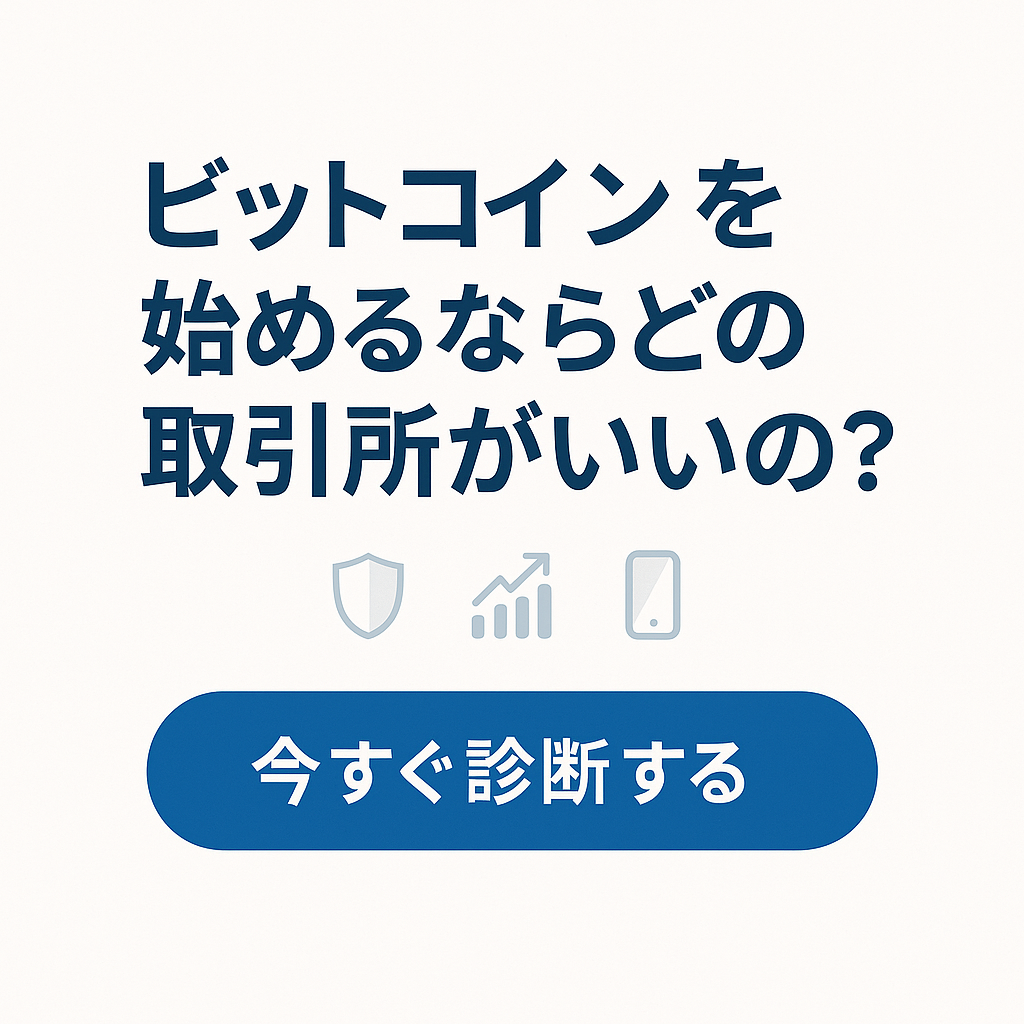目次
米国「Bitcoin for America Act」と日本の暗号資産税制の行方【2025年11月最新版】
結論: 米国では「連邦税をビットコインで納付し、そのまま国家のビットコイン準備金に積み上げる」法案が提出され、日本では105銘柄を金融商品扱い&税率20%前後の分離課税を目指す議論が“最終コーナー”に入っています。ただしどちらもまだ「法案・要望段階」であり、施行は早くても2026年以降という点が重要です。
米国「Bitcoin for America Act」法案の詳細
要約: 2025年11月20日、ウォーレン・デビッドソン下院議員が、連邦税のビットコイン納付と「戦略的ビットコイン準備金」への組み入れを認める「Bitcoin for America Act」を提出しました。
法案の主要ポイント
2025年11月20日、米国のウォーレン・デビッドソン下院議員(共和党・オハイオ州)が、「Bitcoin for America Act(ビットコイン・フォー・アメリカ法案)」を提出しました。法案は、米国民と企業が連邦税をビットコインで納付できるようにする画期的な内容です。
同議員は公式声明で、ビットコイン納税と戦略的ビットコイン準備金の意義を次のように述べています(要旨):
「Bitcoin for America Act は、金融システムを近代化し、何百万人もの米国民が既に日常的に使用しているイノベーションを受け入れる重要な一歩だ」
戦略的準備金への組み入れ
この法案の最大の特徴は、ビットコインで納付された税金が全て「Strategic Bitcoin Reserve(戦略的ビットコイン準備金)」に振り向けられる点です。
- トランプ大統領は2025年3月の大統領令で、押収されたビットコインを売却せず「戦略的準備金」として保有する方針を既に打ち出しています。
- Bitcoin for America Act は、「税金として受け取ったBTCを追加の準備金として積み上げる」新たなルートを作る位置付けです。
ビットコイン・ポリシー・インスティテュート(BPI)などが公開したモデルでは、
- 2026年1月1日〜2030年末までの間に、
- 連邦税の1%がビットコインで支払われるという控えめな前提でも、
- 2.6百万BTC超を蓄積し得ると試算されています(価格水準による)。
キャピタルゲイン税の免除
現行の米国税制では、ビットコインは資産(property)扱いなので、売却や決済に使うたびにキャピタルゲイン税が発生します。
Bitcoin for America Act では、「連邦税の支払いに使ったBTC」についてはキャピタルゲイン課税を免除する仕組みが盛り込まれていると複数の報道で伝えられています。
- これにより、「税金を払ったらその分のキャピタルゲイン税も取られる」という二重課税的な構造を解消し、
- ビットコインを『使いやすい』資産にする狙いがあります。
過去の類似法案との違い
米国では既に複数の「ビットコイン準備金」関連法案が存在しており、今回のBitcoin for America Act はその第三の柱という位置付けです。
| 法案名 | 提出議員 | 主な内容 |
|---|---|---|
| BITCOIN Act of 2025 | シンシア・ルミス上院議員 | トランプ政権の大統領令を法制化しつつ、5年間で最大100万BTC(約800億ドル規模)を購入して戦略的ビットコイン準備金を構築する構想。購入原資は金準備の再評価やFRB利益の活用など「予算中立」な仕組みが想定されている。 |
| Reserve and Stockpile Act(H.R.2112 等) | バイロン・ドナルズ下院議員 | 2025年3月6日の「戦略的ビットコイン準備金とデジタル資産ストックパイル」大統領令を法律として成文化する法案。主眼は「既に押収済みのビットコインやデジタル資産を一元管理し、“売らずに蓄える”ルールを明確化すること」で、新規購入よりも管理・透明性の強化にフォーカスしている。 |
| Bitcoin for America Act | ウォーレン・デビッドソン下院議員 | 「税金支払い」という市場主導のルートでBTCを積み上げる仕組み。政府が巨額のBTCを一気に買うのではなく、国民と企業が自発的に選ぶことで準備金を増やす設計。キャピタルゲイン免除条項により、ビットコイン決済の障壁を下げる狙いもある。 |
特にデビッドソン議員の法案は、「国家がマーケットの大口買い手になる」よりも、「納税という自然なフローの中で徐々にBTCを蓄える」点で、より市場フレンドリーと評価されています。
日本の暗号資産税制の現状と課題
要約: 日本では暗号資産の利益は雑所得として最大55%課税ですが、金融庁・業界団体・与党税調がそろって「20%前後の分離課税+105銘柄の金融商品化」を検討しており、2026年度以降の本格改正が視野に入っています。ただし現時点ではあくまで「方針・要望・報道」であり、正式決定ではありません。
現行の税制と問題点
日本では、暗号資産取引で得た利益は「雑所得」扱いで総合課税です。
- 所得税:5〜45%(累進課税)
- 住民税:一律10%
を合算すると、最大約55%(55〜55.945%)が課される仕組みになっています。
このため、次のような問題が指摘されています。
- 損失の繰越控除ができない
→ 株・FXは3年間の損失繰越が可能だが、暗号資産は認められていない。 - 他の所得との損益通算が限定的
→ 暗号資産同士・同じ雑所得内では通算可能だが、給与・株式譲渡益などとは通算不可。 - 税率が高く国際競争力を損なう
→ 海外の「0〜20%」前後の国と比べて不利で、投資家・事業者の海外流出要因とされる。
金融庁の改革方針(報道ベース)
2025年11月、朝日新聞・ロイターなど複数の報道によると、金融庁は暗号資産を「金融商品取引法(FIEA)の対象とする」方向で制度設計を進めているとされています。
- 対象は、国内の暗号資産交換業者が取り扱う105銘柄。
- これらを「金融商品」として扱い、情報開示義務やインサイダー取引規制、税制の見直しをセットで行う構想です。
報道や業界向け解説を総合すると、検討されている主な論点は次のとおりです。
- 情報開示の義務化
- プロジェクト概要・リスク要因・ブロックチェーン技術の特徴などを、株式と同様に開示。
- インサイダー取引規制
- 上場・上場廃止・重大な技術トラブルなどの「重要事実」について、インサイダー取引規制を導入。
- 申告分離課税の導入(税率20%前後)
- 株・FXと同様に、一律約20%(実務上は20.315%)の分離課税を導入する方向で、金融庁・与党税調・業界団体の要望が概ね一致。
- 損失繰越控除の導入(3年間)
- JVCEA・JCBAの要望では、3年間の損失繰越と、交換タイミング課税の見直しが明記されています。
※これらは「検討・要望・報道」の段階であり、最終的な制度の中身は2025年12月の税制改正大綱・2026年通常国会の審議で確定します。
業界団体(JVCEA・JCBA)の要望活動
JVCEA(日本暗号資産等取引業協会)とJCBA(日本暗号資産ビジネス協会)は、2025年7月30日に「2026年度税制改正に関する要望書」を政府に提出しています。
要望書の骨子は以下の通りです。
- 20%申告分離課税+3年間の損失繰越
- 暗号資産の種類・ウォレットの種類による区分なし(DEXや自社ウォレットも含め一律)
- 現物・デリバティブ取引の双方を対象
- 暗号資産同士の交換時には課税せず、法定通貨に換金した時点でまとめて課税
- 寄附・相続などに関する過度な課税の見直し
さらに自民党ブロックチェーン議連や各種シンクタンクも、
- 株式等との損益通算
- 小額決済の非課税(少額決済特例)
などを含めた“株式並み”の税制への移行を提言しています。
税制改正のスケジュール感
現在想定されている大まかなスケジュールは次の通りです。
- 2025年11〜12月
- 金融審議会WG 終盤の整理
- 与党税制調査会で「暗号資産税制」の扱いを協議
- 2025年12月
- 「2026年度税制改正大綱」にどこまで盛り込まれるかが最初の関門。
- 2026年通常国会(1〜6月)
- 金商法改正案・税制関連法案の審議
- 施行時期
- 早ければ2026年分の所得(2027年申告)から、遅くとも2027年分からという見込みが一般的です。
今後予想される変化と投資家への影響
要約:
- 米国:ビットコインが「税金支払いに使える準準備通貨」という位置づけになれば、国家レベルの需要増が起こり得ます。
- 日本:20%分離課税+損失繰越+交換時課税の見直しが実現すると、暗号資産は株式やFXに近い「普通の投資商品」に近づきます。
グローバル市場への影響
米国で連邦税のビットコイン納付が認められた場合、次のような影響が想定されています。
- 国家レベルでBTCを“売らずに貯める”プレイヤーが増える
- 「税金として払われたBTC」が市場に戻らず、循環供給を圧縮
- 他国・州レベルでも「ビットコイン準備金」構想が連鎖(テキサス・アリゾナ・ニューハンプシャーなど既に動きあり)
これらはすべて「法案・政策次第」ですが、ビットコインが“デジタル金”として中央銀行・財務省のバランスシートに本格的に乗り始める流れは、2025年時点でかなり現実味を帯びてきています。
日本の投資家にとってのメリット(想定)
税制改正がほぼ要望どおり実現した場合、日本の個人投資家にとっては次のような変化が期待できます。
1. 税負担の大幅軽減
例として、「暗号資産の利益が300万円」のケースで比較してみます(ざっくりイメージ用)。
| 項目 | 現行制度(雑所得・総合課税) | 改正後イメージ(申告分離課税) |
|---|---|---|
| 課税方式 | 総合課税(他の所得と合算) | 申告分離課税(他の所得と切り離し) |
| 想定税率 | 約30%前後(所得階層により変動) | 一律20.315%(所得税+住民税) |
| 納税額(利益300万円) | 約90万円 | 約61万円 |
| 差額 | – | 約29万円の節税 |
※ 上記はあくまで概算イメージです。実際の税額は年収・控除・他の所得により変動します。
2. 損失繰越による投資戦略の柔軟化
- 3年間の損失繰越が実現すれば、
- 「今年はマイナスだけど、来年・再来年のプラスと相殺できる」
- 「含み損ポジションの整理」をしやすくなる
- 「大きくリスクを取る年」と「守りに徹する年」を、税務上も設計しやすくなる
3. 交換時課税の見直し(DeFi・NFTにも追い風)
- 暗号資産同士の交換では課税せず、法定通貨に換えたタイミングでだけ課税という案が通れば、
- DeFi・NFT・GameFi などの“オンチェーン経済”の回転がかなり楽になる
- 損益計算の手間も大幅に軽減される
取引所選びの重要性
制度が変わるときほど、「どの取引所を使うか」が効いてきます。
- 対象105銘柄をどれだけカバーするか
- 税務レポート・年間取引報告の充実度
- 積立・レンディング・ステーキングなど、長期運用サービスの有無
などを基準に、自分の投資スタイルに合った取引所を今のうちに決めておくのが得策です。
日本の主要仮想通貨取引所
BitTrade(ビットトレード)
特徴
- 豊富な暗号資産銘柄を取り扱い(46銘柄前後)
- 高度なセキュリティシステム
- 初心者から上級者まで対応のUI/UX
主要手数料
- 売買手数料:販売所スプレッド、取引所 無料
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:330円
- 送金手数料:銘柄により異なる
最小購入額:販売所500円、取引所0.00001BTCかつ2円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
向いているユーザー:多様な銘柄への分散投資を検討している方
SBI VCトレード
特徴
- SBIグループの信頼性と実績
- 業界最低水準の手数料体系
- 充実したレンディング/ステーキング/積立
主要手数料
- 売買手数料:無料(現物)
- 入出金手数料:無料
- 送金手数料:無料(ネットワーク手数料相当は別途)
取扱銘柄:36銘柄 最小購入額:1円〜(取引所)/販売所は銘柄により異なる
積立サービス:毎月500円から レンディング:年率は募集時条件により変動
セキュリティ:金融庁認可業者の高度なセキュリティ
向いているユーザー:手数料を最小限に抑えたい初心者〜中級者
Coincheck(コインチェック)
特徴
- 国内最大級の暗号資産取引所
- 初心者にも分かりやすいシンプルな操作性
- NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」運営
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所は銘柄ごとに設定(BTC/ETHは無料対象)
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:407円
- 送金手数料(BTC):0.0005 BTC
取扱銘柄:35銘柄 最小購入額:500円
積立サービス:月1万円から(対応銘柄は拡充傾向)
特別サービス:Coincheck NFT、IEO実施経験
向いているユーザー:暗号資産初心者、NFTに興味がある方
bitbank(ビットバンク)
特徴
- 全暗号資産取引量 国内No.1の実績(媒体報道)
- 高度な取引ツールとチャート機能
- Maker手数料マイナス(報酬システム)
主要手数料
- 売買手数料:Maker -0.02%/Taker 0.12%
- 入金手数料:無料(クイック入金等は条件あり)
- 出金手数料:550円/770円(3万円以上)
- 送金手数料(BTC):0.0006 BTC
取扱銘柄:国内最多クラス(40銘柄以上) 最小購入額:0.0001 BTC
積立サービス:定期購入あり(最小100円〜、販売所)
セキュリティ:コールドウォレット、マルチシグ対応
特殊機能:リアルタイム入金、高度な注文機能
向いているユーザー:取引量の多いアクティブトレーダー、上級者
OKJ(オーケージェー)
特徴
- 世界大手OK Groupの日本法人による運営
- 業界トップクラスの狭いスプレッド
- 高利回りFlash Dealsやステーキングサービス
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所 Maker 0.07%/Taker 0.14%(基準) ※取引量で優遇あり
- 入金手数料:無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料(日本円):100万円未満 400円/100万〜1,000万円未満 770円/1,000万円以上 1,320円
- 送金手数料:銘柄により異なる(例:IOSTは低コスト)
取扱銘柄:50銘柄(2025年11月時点、MEME上場反映) 最小購入額:500円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
独自サービス:Flash Deals(高利回りの実績)、マルチチェーン対応
向いているユーザー:スプレッド重視、多様な銘柄に分散投資、レンディング/ステーキングに興味がある方
bitFlyer(ビットフライヤー)
特徴
- ビットコイン取引量9年連続 国内No.1
- 創業以来ハッキング被害ゼロの高度なセキュリティ
- 1円から取引可能な初心者に優しい設計
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所0.01~0.15%(取引量により変動)
- 入金手数料:住信SBIネット銀行 無料、その他銀行 330円(クイック入金)
- 出金手数料:三井住友銀行 220円/440円、その他 550円/770円
- 送金手数料(BTC):0.0004 BTC(XRP・MONA・XLM等は無料)
取扱銘柄:39銘柄(現物) 最小購入額:1円
積立サービス:対応 レバレッジ取引:bitFlyer Lightningで最大2倍(BTC、ETH対応)
セキュリティ:マルチシグ、コールドウォレット、2段階認証
特別サービス:bitFlyer クレカ(利用額の0.5~1.0%をBTC還元)、ビットコインをもらう、IEO実績
向いているユーザー:少額から始めたい初心者、取引量の多いアクティブトレーダー、レバレッジ取引に興味がある方
よくある質問(FAQ)
Q1. 米国の法案が成立すると、日本にどのような影響がありますか?
A. 日本の税制改正や規制議論を後押しする“心理的インパクト”が大きいと考えられます。
- 米国が「税の支払いにビットコインを認め、国家準備金として保有する」動きを強めれば、
- 暗号資産=単なる投機商品、というイメージから
- 「国家レベルで保有される準備資産」というイメージへのシフトが進みます。
- これに合わせて、
- 日本でも分離課税・金商法適用の議論が加速する可能性が高いです。
ただし、日本が「税金をビットコインで納められる国」になるかどうかは別問題で、当面は税制(20%分離課税)と金融商品化が優先テーマになっています。
Q2. 日本の税制改正はいつから適用されますか?
A. 早くても「2026年分の所得(2027年申告)」からという見方が一般的です。
- 2025年11月:金融庁の方針が報道され、与党税調で議論が本格化。
- 2025年12月:「2026年度税制改正大綱」への掲載が最初の関門。
- 2026年通常国会で関連法案成立 → 施行は2026年または2027年から、というシナリオが多くの専門家の見立てです。
Q3. 現在の雑所得と将来の分離課税では、どのくらい税金が違いますか?
A. 所得が大きい人ほど節税効果が大きくなります。
暗号資産の利益が500万円の場合のざっくり比較イメージ:
| 年収 | 現行制度(雑所得・総合課税) | 分離課税(20.315%)のイメージ | 節税額(目安) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約150万円(税率30%想定) | 約102万円 | 約48万円 |
| 700万円 | 約183万円(税率36〜37%想定) | 約102万円 | 約81万円 |
| 1000万円 | 約238万円(税率47%前後想定) | 約102万円 | 約136万円 |
※ 控除・家族構成などで実際の税額は変わります。上記はイメージです。
Q4. 税制改正前に暗号資産投資を始めるのは損ですか?
A. 「長期保有を前提に、利益確定をいつ行うか」で変わります。
- メリット
- 税制改正前に買っておいたBTC・ETHが、その後の価格上昇の恩恵を受ける可能性
- 早めに市場の値動きや税務の実務に慣れることができる
- デメリット
- 改正前に大きな利益確定をすると、現行の最大55%課税が適用される
一つの現実的な戦略案
- 今は「少額積立+学習フェーズ」と割り切る
- 税制改正後を見据え、長期保有用ポジションを中心に構築
- 利確のタイミングは、改正内容を確認してから本格検討
Q5. 「105銘柄」の対象通貨は何ですか? すべて分離課税の対象になりますか?
A. ビットコイン・イーサリアムなど、国内取引所で取り扱われる主要銘柄が中心になる見込みです。
- 報道によれば、国内第一種登録業者が扱う119銘柄のうち、105銘柄を優先的に「金融商品」扱いする方向とされています。
- そこに含まれるのは、
- BTC / ETH / XRP / LTC / BCH / ADA / DOT / SOL などの主要銘柄はほぼ確実と見られます。
ただし、
- 正式リストは金融庁からまだ公表されていません。
- 海外取引所のみで扱われるマイナー銘柄などは、当面は対象外(=従来どおり雑所得扱い)の可能性もあります。
Q6. 海外取引所を使っている場合も、新しい分離課税の恩恵を受けられますか?
A. 現時点では「国内取引所での取引が中心に想定されている」と考えた方が安全です。
- 報道や要望書では、国内交換業者が取り扱う105銘柄が制度設計の前提になっています。
- 海外取引所での取引について、
- どこまで分離課税の対象に含めるかは、まだ公式な整理がありません。
そのため、
- 大きな利益確定は、制度詳細が固まるまで待つ
- 中長期的には、国内取引所へのポジション移管も視野に入れておく
- 具体的な判断は、税理士など専門家に相談
といった慎重な対応が推奨されます。
まとめ:暗号資産投資は「税制の大転換期」に入った
- 米国では、
- 「税金をビットコインで納める」Bitcoin for America Act
- 「100万BTC購入」を視野に入れたBITCOIN Act of 2025
- 戦略的ビットコイン準備金をめぐる大統領令・連邦/州レベルの法案
が同時並行で進んでおり、ビットコインが国家レベルの準備資産として扱われ始めています。
- 日本でも、
- 金融庁が105銘柄の「金融商品」化+インサイダー規制・開示義務を検討
- JVCEA・JCBAが20%申告分離課税+3年損失繰越+交換時課税見直しを要望
- 与党税調・税制改正大綱で、2026年度以降の本格改正を議論中
と、「最大55%課税→約20%課税」へのシフトが現実味を帯びています。
今からできる4つのアクション
- 最新情報をウォッチする
- 金融庁・JVCEA・JCBA・主要取引所の公式発表をチェック
- 取引所を選ぶ(or 見直す)
- 105銘柄への対応・税務レポート・積立サービスの有無などで比較
- 少額から経験値を貯める
- 税制改正前は「少額・積立・長期目線」で市場に慣れる
- 長期戦略と税務をセットで考える
- 「いつ買うか」と同じくらい、「いつどのくらい利確するか」を意識する
参考資料・出典
(記事内で引用した主な公的・一次情報ソース)
- 米国関連
- Rep. Warren Davidson 公式声明「Rep. Warren Davidson Introduces the Bitcoin For America Act」(Congressman Warren Davidson)
- White House「Establishment of the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile」(ホワイトハウス)
- S.954 BITCOIN Act of 2025(Cynthia Lummis 上院議員)(Senator Cynthia Lummis)
- 日本の規制・税制関連
- 金融庁「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」資料
- 朝日新聞/ロイター「暗号資産105銘柄を金融商品として扱う方針」報道(Reuters)
- JVCEA・JCBA「2026年度税制改正に関する要望書」(一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA))
- 解説・二次情報(税制・投資家向け)
- CoinPost, Coincheck, Cryptact などの最新解説記事(コインポスト)
免責事項
本記事は執筆時点(2025年11月21日)の情報に基づく一般的な情報提供であり、特定の投資判断・税務アドバイスを行うものではありません。
- 税制・法律は今後変更される可能性があります。
- 実際の申告・節税・投資判断については、必ず税理士・弁護士など専門家にご相談ください。
- 暗号資産は価格変動が大きく、元本割れのリスクがあります。投資は余裕資金の範囲内で、自己責任にて行ってください。