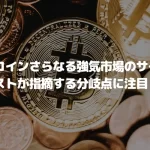目次
シティグループの警告内容
要約:
シティグループは2025年11月25日付のレポートで、ビットコインが「半減期サイクルの歴史的に弱い2年目」に入りつつあると警告し、2025年10月10日以降の米国ビットコインETFからの資金流出額が約40億ドルに達したと指摘しました。
警告の核心:半減期サイクル2年目の冷え込み
シティのアナリストは、2024年4月の第4回ビットコイン半減期から時間が経過する中で、現在は「半減期サイクルの2年目にあたり、歴史的に価格モメンタムが弱くなりやすい局面」に入っていると分析しています。
シティグループの主要指摘事項(概要):
- ETFからの大規模流出
- 2025年10月10日以降、米国上場のビットコイン現物ETFからの純流出額が合計40億ドル近くに達した。
- 長期保有者の慎重姿勢
- ドイツ銀行などの分析と同様、オンチェーンデータをもとに長期保有者(1年以上保有)の利益確定売りが増加している点を警戒。
- 半減期効果の減衰(すでに織り込み済み)
- 2024年の半減期前後で、ETF経由の資金流入などを通じて半減期期待が先行してしまい、「半減期そのものが新たな上昇材料になりにくい」と指摘。
- ベアケースシナリオ(弱気シナリオ)への接近
- シティは10月時点のレポートで、景気後退シナリオではビットコインが8万3,000ドル前後まで下落する可能性を挙げていましたが、11月の急落により「年末の弱気シナリオである8万2,000ドルに近づきつつある」と警告しています。
シティの価格予測の変遷
2025年10月時点で、シティは以下のような価格目標を提示していました:
| 発表時期 | 12カ月目標価格 | 2025年末予測 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 18万1,000ドル | 13万3,000ドル | ETF流入継続を前提とした強気寄りシナリオ |
| 2025年11月時点 | 変更検討中(下方修正の可能性) | 13万3,000ドル目標は据え置きだが達成リスク増大 | ビットコインは約8万6,000ドル前後で推移 |
※2025年11月25日時点で、ビットコインは約8万6,000ドルで取引されており、シティが10月に示した年末13万3,000ドル予測と現状のギャップが大きくなっています。
「半減期サイクル2年目」とは何か
ビットコインは約4年ごとにマイニング報酬が半分になる「半減期」を迎え、その周期ごとに**「4年サイクル」**として語られることが多くなっています。
一般的な半減期サイクルのパターン:
- 1年目(半減期が起きる年)
└ 供給減少期待から徐々に価格が上向き、半減期前後〜その後に向けて上昇が加速。 - 2年目
└ 歴史的に調整局面となりやすく、最も弱気になりやすい年。 - 3年目
└ 再度の上昇局面入り、価格が落ち着きながら高値を伺う。 - 4年目
└ 強気相場のピークをつけやすく、史上最高値更新が起きやすい。
今回の第4回半減期(2024年4月)から見ると、2025年後半〜2026年にかけてが「2年目〜3年目の移行ゾーン」にあたり、
シティは「歴史的には冷え込みやすいタイミングに入った」との視点から警鐘を鳴らしています。
半減期サイクルとは?過去との比較
要約:
ビットコインの半減期は約4年ごとに発生し、過去3回はいずれも半減期から1〜2年後に強力な強気相場が訪れました。しかし、第4回半減期後の今回のサイクルでは、上昇力が明らかに鈍いという特徴があります。
半減期の基本メカニズム
半減期(Halving)とは?
- 約21万ブロック(約4年)ごとに、マイナーが獲得するビットコイン報酬が半分になるイベント。
- インフレ率を段階的に低下させ、最終的な発行上限2,100万BTCに近づけていく仕組み。
過去の半減期と価格パターンの比較
第1回半減期(2012年11月28日)
- 報酬:50 BTC → 25 BTC
- 半減期直前の価格:約12ドル
- 半減期後約1年強のピーク:約1,150ドル(約96倍)
第2回半減期(2016年7月9日)
- 報酬:25 BTC → 12.5 BTC
- 半減期時の価格:約650ドル
- 約1年半後(2017年12月)のピーク:約2万ドル(約30倍)
第3回半減期(2020年5月11日)
- 報酬:12.5 BTC → 6.25 BTC
- 半減期時の価格:約8,700ドル
- 約1年半後(2021年11月)のピーク:約6万9,000ドル(約8倍)
第4回半減期(2024年4月19〜20日)
Fidelity Digital Assets のレポートによると
- 報酬:6.25 BTC → 3.125 BTC
- 半減期時(2024年4月19日)の価格:約63,762ドル
- 半減期から約1年後(2025年4月15日)の価格:83,671ドル(+31%)
- 2025年10月6日の史上最高値:約12万6,000ドル超
- その後の調整を経て、2025年11月時点の価格:約8万6,000ドル(半減期時点から約+36%)
今回の半減期が異なる点
過去3回と比べた大きな違い:
| 比較項目 | 過去3回の平均イメージ | 第4回(2024年半減期) |
|---|---|---|
| 半減期から1年後の上昇率 | +300〜500% | +30%前後(2025年4月時点) |
| 半減期からピークまでの期間 | 13〜19ヶ月程度 | 約6ヶ月(2024/4 → 2025/10) |
| ピークからの下落幅 | −80%前後も多い | 現時点で約−30〜35% |
| 機関投資家の関与 | 低〜中 | 高い(ETF経由の参加が顕著) |
| 現物ETFの存在 | なし | あり(構造的な変化) |
Fidelityは「今回のサイクルは過去よりも上昇ペースが緩やかで、価格よりもネットワークや制度面の成熟が目立つ」と総括しており、「半減期=即大相場」だった過去サイクルと同じ図式では語りにくくなっていると指摘しています。
今回の半減期が異なる5つの理由
要約:
2024年以降のビットコインは、「現物ETFの存在」「機関投資家主導」「高金利環境」「規制不透明」「長期保有者の売り」という新しい条件の下で動いており、従来の単純な半減期パターンから外れつつあります。
1. 現物ETFの登場による市場構造の変化
2024年1月に米国でビットコイン現物ETFが承認・上場したことで、ビットコインへの投資経路は大きく変わりました。
主な影響:
- 機関投資家や年金基金などが、証券口座からビットコインにアクセス可能に
- 2024年〜2025年半ばまでに、米スポットETFには累計数百億ドル規模の資金が流入
- 一方で、2025年11月時点では11月単月だけで約35億ドルの純流出が発生し、価格下押し要因になっている。
Citi Research は、
「ETFから10億ドルの資金流出があるごとに、ビットコイン現物価格は概ね3.4%下押しされる」
と推計しており、今回の40億ドル近い流出のインパクトの大きさを強調しています。
2. 機関投資家主導の市場への転換
2020年の半減期前後は依然として個人投資家中心の相場でしたが、2024年以降は明確にETFを通じた機関投資家の影響が拡大しています。
- 13Fレポート等から、米スポットETFの保有者には
- 年金基金
- 大手機関投資家(バロンズ、Coindesk等の報道)
- ヘッジファンド
などが多数含まれることが確認されています。
機関投資家は、
- 四半期決算やリスク管理ルールに従って機械的にリバランス(売買)する
- マクロ指標や金利動向に敏感に反応する
- レバレッジ戦略や裁定取引を組み合わせる
といった特徴があり、価格の「勢い任せの上昇」だけでなく、「急速な資金引き上げ」による調整も起こしやすい構造になっています。
3. マクロ経済環境の劇的な変化
過去の半減期は、どれも「低金利〜金融緩和」の追い風がありましたが、今回は真逆です。
- 2022〜2024年にかけてFRBは急速な利上げを実施
- 2025年時点でも10年米国債利回りは4%台前後で推移し、実質金利もプラス圏を維持
その結果:
- 「無リスク資産」である国債だけでも4%前後の利回りが得られる
- ゼロ金利環境で輝いていた「非利回り資産」としてのビットコインの相対的魅力は低下
という構図になっており、過去の半減期と同じような「金融相場的な爆上げ」を期待しにくい環境です。
4. 規制環境の不透明感
ドイツ銀行や欧州中央銀行(ECB)のレポートは、規制の方向性が明確でないことが暗号資産市場のリスク要因になっていると指摘しています。
- 米国では、
- デジタル資産の明確な法的区分を目指す複数の法案(FIT21 や CLARITY 関連法案など)が政治的対立により足踏み。
- EUではMiCA規制が順次導入される一方、ステーブルコインやDeFiなどの扱いで実務レベルの不確実性が残存。
- 日本でも、暗号資産課税の見直し(申告分離課税化など)が議論されているものの、まだ制度変更前の状態。
こうした要因が、長期マネーの本格参入を鈍らせる一因となっています。
5. 長期保有者(HODLer)の行動変化
ドイツ銀行のレポートは、今回の下落局面について
- 「長期保有者による利益確定売り」が顕著である
- 直近の調整で、暗号資産全体の時価総額は約1兆ドル(約157兆円)消失した
と分析しています。
シティも、同様に長期保有者の慎重姿勢を指摘しており、
- 1年以上保有されていたコインの一部が取引所へ移動し、
- ETFからの資金流出と重なることで「上値の重さ+下値の脆さ」を生み出しているとみています。
機関投資家の動向変化
要約:
現物ETFの登場により機関投資家がビットコイン市場の中核プレイヤーとなりましたが、2025年10月以降はETFからの大規模な資金流出が発生。一方で、マイクロストラテジーのように長期的な買い増しを続けるプレイヤーも存在します。
ETFからの資金流出の詳細
Coindesk Japan や Phemex などの集計によると
- 2025年11月単月で、米国のビットコイン現物ETFから約35億ドルの純流出
- これは2024年2月の記録的な流出額(約33億ドル)に匹敵する規模
- BlackRock の IBIT だけで約22億ドルの流出という試算もあり、市場のセンチメント悪化がETF経由で増幅された格好
Citi Research の試算では、
「ETFからの純流出10億ドルごとに、ビットコイン現物価格はおおよそ 3.4% 押し下げられる」
とされており、35〜40億ドル規模の流出は10%超の価格押し下げ圧力になり得ると警戒されています。
機関投資家が売る主な理由
- 四半期・年末決算に向けた利益確定
- ポートフォリオのリバランス(ビットコイン比率が上がり過ぎた分の調整)
- FRBの政策・株式市場のボラティリティに応じたリスク縮小
MarketWatch などの報道でも、ETFを通じて参入した「ファストマネー(短期志向の機関投資家)」の動きが調整局面を増幅していると指摘されています。
それでも買い続けるプレイヤー:マイクロストラテジーなど
一方で、マイクロストラテジー(MicroStrategy)は
- 2024年11月時点で 386,700 BTC を保有し、
- 平均取得単価は1BTCあたり約56,761ドルであることを公表しています。
その後の追加購入状況については2025年11月時点で確定情報が出揃っていないものの、
同社は「企業財務としてビットコインを長期保有する」というスタンスを一貫しており、短期のボラティリティよりも長期の価値保存機能を重視した戦略を続けているとみられます。
こうした「長期ガチホ型」機関投資家と、「ETF経由の短期マネー」が同時に存在している点が、現在の市場の複雑さを象徴しています。
他の金融機関の見解
要約:
シティグループは警鐘寄りのトーンですが、他の大手金融機関は「短期は調整、長期は強気」というスタンスが多いのが現状です。
主要金融機関の価格予測比較(2025年10〜11月時点)
| 金融機関 | 2025年末予測 | 12カ月〜中期予測 | 根拠の方向性 |
|---|---|---|---|
| シティグループ | 約13万3,000ドル | 12ヶ月で18万1,000ドル | ETFフローとマクロ次第で、8万3,000〜15万6,000ドルまで広いレンジを想定。 |
| JP Morgan | 16万5,000ドル | 6〜12ヶ月で17万ドル前後 | 金とのボラ調整比較から「現在は割安」と判断。 |
| ドイツ銀行 | 8万〜10万ドル | 中期で15万ドル程度も | マクロ逆風と市場構造の脆弱性を強調。 |
| スタンダードチャータード | 20万ドル | 2028年までに50万ドル | ETF普及とボラ低下により、長期では大幅上昇を予想。 |
ドイツ銀行のレポートは特に、
- 10月初旬のピークから約35%の下落で、
- 暗号資産市場全体の時価総額が約1兆ドル(約157兆円)消失した
と指摘し、今回の調整が「単なる一時的な押し目」なのか、それとも「より深いリセット」の入り口なのか、冷静な見極めが必要だと述べています。
投資家が取るべき対応策
要約:
シティの「半減期サイクル2年目の冷え込み」警告を踏まえると、短期の値動きを当てにするよりも、リスク管理と長期戦略に重点を置いた対応が重要になります。
ここから先は、一般的なリスク管理の観点であり、特定の投資行動を推奨するものではありません。
1. 現在のポジションとリスク許容度の棚卸し
まずは、自分自身の状況を俯瞰します。
- 平均取得単価はいくらか
- ビットコイン・暗号資産への投資額が、総資産の何%になっているか
- 投資期間(短期〜長期)と、許容できる最大損失額
多くの金融機関やアドバイザーは、暗号資産への投資比率は総資産の5〜10%以内を一つの目安として挙げています。
2. シナリオ別の構え方(例)
- 「長期強気」派
- 一括ではなく積立(ドルコスト平均法)で買い下がる
- 7〜8万ドル台の大きな調整を「長期の買い場」とみなす
- 「様子見」派
- 一部を利益確定し、現金比率を引き上げる
- FRBの方針やETFフローの転換を待ってから追加投資
- 「短期は弱気」派
- いったんポジションを縮小し、さらに下落したタイミングでの再エントリーを検討
どのシナリオでも共通して重要なのは、
「事前にルールを決めておき、感情で判断しない」
ことです。
3. 半減期サイクルを意識した長期戦略
過去のサイクルでは、「半減期2年目の調整局面」が結果的に長期的な最良の買い場になってきたケースも多くありました。
- もちろん今回も同じになる保証はありませんが、
- 「今すぐ大きく張るかどうか」ではなく、
- 2025〜2026年を通じて分散してポジションを作るという発想は、リスクを抑えやすいアプローチです。
4. 税金と記録管理(日本)
- 現行では、ビットコイン等の暗号資産の売買益は雑所得として総合課税(最大55%)。
- 2026年度以降に申告分離課税(20.315%)への移行が検討されていますが、まだ施行前です。
取引が増えるほど損益計算・申告作業は複雑になるので、
- 取引所の年間取引報告書をダウンロードして保管
- スプレッドシート等で取引履歴を整理
- 必要であれば税理士への相談
といった準備を早めに進めておくことが重要です。
半減期後の長期見通し
要約:
短期的には「半減期サイクル2年目の調整」が意識されているものの、2026〜2028年にかけての長期見通しを強気に見る金融機関は依然として多いのが現状です。
2026〜2028年の代表的シナリオ
スタンダードチャータードのジェフリー・ケンドリック氏は、
- 2025年末:20万ドル
- 2028年末:50万ドル
という非常に強気な価格パスを示しており、これが実現する確率はともかく、長期的な需要拡大とボラティリティ低下を前提とした強気スタンスを維持しています。
一方で、JP Morgan や Goldman Sachs は、
- 2025年末:10万〜16万5,000ドル程度
- 2028年:20〜30万ドル前後
といった、より現実的なレンジを提示しつつ、「長期的な上昇余地は依然として大きい」という点では一致しています。
供給面から見た長期の支え
Fidelity や複数のリサーチによると:
- 2025年時点で、既にビットコインの発行済み枚数は約1,980万BTC(上限の94%前後)
- 2028年の次回半減期後には、年間インフレ率は0.4%台まで低下
- ゴールドの供給増加率(約1.5%)と比較しても、ビットコインの希少性は時間とともに高まり続ける
という構造的な背景があります。
日本の主要仮想通貨取引所
BitTrade(ビットトレード)
特徴
- 豊富な暗号資産銘柄を取り扱い(46銘柄前後)
- 高度なセキュリティシステム
- 初心者から上級者まで対応のUI/UX
主要手数料
- 売買手数料:販売所スプレッド、取引所 無料
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:330円
- 送金手数料:銘柄により異なる
最小購入額:販売所500円、取引所0.00001BTCかつ2円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
向いているユーザー:多様な銘柄への分散投資を検討している方
SBI VCトレード
特徴
- SBIグループの信頼性と実績
- 業界最低水準の手数料体系
- 充実したレンディング/ステーキング/積立
主要手数料
- 売買手数料:無料(現物)
- 入出金手数料:無料
- 送金手数料:無料(ネットワーク手数料相当は別途)
取扱銘柄:36銘柄 最小購入額:1円〜(取引所)/販売所は銘柄により異なる
積立サービス:毎月500円から レンディング:年率は募集時条件により変動
セキュリティ:金融庁認可業者の高度なセキュリティ
向いているユーザー:手数料を最小限に抑えたい初心者〜中級者
Coincheck(コインチェック)
特徴
- 国内トップクラスの暗号資産取引所
- 初心者にも分かりやすいシンプルな操作性
- NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」運営
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所は銘柄ごとに設定(BTC/ETHは無料対象)
- 入金手数料:銀行振込無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料:407円
- 送金手数料(BTC):0.0005 BTC
取扱銘柄:35銘柄 最小購入額:500円
積立サービス:月1万円から(対応銘柄は拡充傾向)
特別サービス:Coincheck NFT、IEO実施経験
向いているユーザー:暗号資産初心者、NFTに興味がある方
bitbank(ビットバンク)
特徴
- 全暗号資産取引量 国内トップクラスの実績(媒体報道)
- 高度な取引ツールとチャート機能
- Maker手数料マイナス(報酬システム)
主要手数料
- 売買手数料:Maker -0.02%/Taker 0.12%
- 入金手数料:無料(クイック入金等は条件あり)
- 出金手数料:550円/770円(3万円以上)
- 送金手数料(BTC):0.0006 BTC
取扱銘柄:国内最多クラス(40銘柄以上) 最小購入額:0.0001 BTC
積立サービス:定期購入あり(最小100円〜、販売所)
セキュリティ:コールドウォレット、マルチシグ対応
特殊機能:リアルタイム入金、高度な注文機能
向いているユーザー:取引量の多いアクティブトレーダー、上級者
OKJ(オーケージェー)
特徴
- 世界大手OK Groupの日本法人による運営
- 業界トップクラスの狭いスプレッド
- 高利回りFlash Dealsやステーキングサービス
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料、取引所 Maker 0.07%/Taker 0.14%(基準) ※取引量で優遇あり
- 入金手数料:無料(振込手数料は利用者負担)
- 出金手数料(日本円):100万円未満 400円/100万〜1,000万円未満 770円/1,000万円以上 1,320円
- 送金手数料:銘柄により異なる(例:IOSTは低コスト)
取扱銘柄:50銘柄(2025年11月時点、MEME上場反映) 最小購入額:500円
積立サービス:対応 スマホアプリ:高機能アプリあり
セキュリティ:コールドウォレット、2段階認証
独自サービス:Flash Deals(高利回りの実績)、マルチチェーン対応
向いているユーザー:スプレッド重視、多様な銘柄に分散投資、レンディング/ステーキングに興味がある方
bitFlyer(ビットフライヤー)
特徴
- ビットコイン取引量9年連続 国内トップクラス
- 創業以来ハッキング被害ゼロの高度なセキュリティ
- 1円から取引可能な初心者に優しい設計
主要手数料
- 売買手数料:販売所無料(スプレッドあり)、取引所0.01~0.15%(取引量により変動)
- 入金手数料:住信SBIネット銀行 無料、その他銀行 330円(クイック入金)
- 出金手数料:三井住友銀行 220円/440円、その他 550円/770円
- 送金手数料(BTC):0.0004 BTC(XRP・MONA・XLM等は無料)
取扱銘柄:39銘柄(現物) 最小購入額:1円
積立サービス:対応 レバレッジ取引:bitFlyer Lightningで最大2倍(BTC、ETH対応)
セキュリティ:マルチシグ、コールドウォレット、2段階認証
特別サービス:bitFlyer クレカ(利用額の0.5~1.0%をBTC還元)、ビットコインをもらう、IEO実績
向いているユーザー:少額から始めたい初心者、取引量の多いアクティブトレーダー、レバレッジ取引に興味がある方
よくある質問(FAQ)
Q1. 「半減期サイクル2年目」の弱気パターンは本当に再現されるのですか?
A. 過去3回のサイクルでは「2年目に調整」が何度も確認されていますが、今回はETFや機関投資家の比重が大きく、過去と同じパターンになる保証はありません。
- 2013年・2017〜2018年・2022年はいずれも
- 半減期後の強気相場 → 2年目に大きな調整
という流れが見られました。
- 半減期後の強気相場 → 2年目に大きな調整
- ただし今回は、
- 現物ETFの存在
- 機関投資家による大量のETFフロー
- 高金利環境
といった、新しい要因が複数絡んでいます。
シティグループは「過去データ上、2年目は冷え込みやすい」と警告していますが、
あくまで「確率が高いパターン」であり、絶対ではありません。
Q2. ETFからの資金流出はいつ止まりますか?
A. FRBの方針や株式市場の落ち着き具合など、「マクロ環境次第」であり、明確なタイミングを断言することはできません。
Citi やドイツ銀行のレポートでは
- 利下げ再開などで「金利ピークアウト感」が強まる
- 株式市場全体のリスクオフが一巡する
- ビットコイン価格が一定の底値(例:7〜8万ドル台)で下げ止まる
といった条件が整わない限り、ETFからの断続的な資金流出が続く可能性があると見ています。
Q3. 今から買うべきか、それとももっと下がるのを待つべきですか?
A. 短期の値動きは誰にも読めません。長期投資を前提とするなら、「一括ではなく積立で時間分散する」という妥協点が現実的です。
- 買う側の論理:
- 史上最高値(12万6,000ドル)から約30%下落している
- 半減期2年目の調整局面は、歴史的に長期投資家にとって「良い買い場」であったことが多い
- 待つ側の論理:
- ETFからの資金流出が続いている
- シティやドイツ銀行は8万〜8万3,000ドルといった「弱気シナリオ」を提示している
どちらの考え方に立つとしても、一度に大金を投じるのではなく、少額の積立で時間を味方につけるのが、リスクを抑えつつ市場に参加する現実的な方法です。
Q4. 過去の半減期と今回で、最も大きな違いは何ですか?
A. もっとも大きいのは、「現物ETFの存在と機関投資家の比重」です。
- 2020年までは、
- 個人投資家と一部の先進的な機関投資家(MicroStrategy や Tesla など)が中心でした。
- 2024年以降は、
- BlackRock や Fidelity などが運用する現物ETFを通じて、
- 年金基金・銀行・ヘッジファンドなどの本格的な機関マネーが参入。
その結果、
- 価格がマクロ環境や金利に敏感になった
- ETFの資金フローが価格変動の増幅装置になった
- 「ガチホ」中心の個人主導相場よりも、一喜一憂しやすい構造になった
という変化が起きています。
Q5. シティグループの警告はどの程度信頼できますか?
A. 世界的大手銀行としての分析力は高い一方、「暗号資産の価格予測」はどの機関であっても外れることが少なくありません。
事実として:
- シティは2025年10月に
- 2025年末:13万3,000ドル
- 12ヶ月目標:18万1,000ドル
を出しつつ、同時に弱気シナリオとして8万3,000ドルも想定していました。
このように、1つの数字ではなく「レンジと前提条件」で見るべきであり、
- ETFフロー
- 半減期サイクル
- マクロ環境
といった「論点そのもの」は参考にしつつ、具体的な価格水準はあくまで一つのシナリオとして扱うのが現実的です。
まとめ
- シティグループは、
- 10月10日以降のビットコインETFからの約40億ドルの資金流出と、
- 半減期サイクル2年目の歴史的な弱さ
に着目し、「ビットコイン市場の冷え込み」に警告を発しました。
- ドイツ銀行も、
- 10月初旬のピークからの約35%下落で、暗号資産市場全体から約1兆ドル(約157兆円)の時価総額が消失したことを指摘し、
- 市場構造の脆弱さとマクロリスクを強調しています。
- 一方で、
- JP Morgan は年末16万5,000ドル、
- スタンダードチャータードは2025年末20万ドル・2028年50万ドルという強気シナリオを維持しており、
- 「短期は調整、長期は強気」という見方が主流なのも事実です。
投資家にとって重要なのは:
- シティや他行のレポートを「当たる・外れる」で見るのではなく、
どの前提が崩れるとシナリオが変わるのかを理解すること。 - 一括投資よりも、
ドルコスト平均法(積立)とポートフォリオ分散でリスクを抑えること。 - 半減期サイクル2年目は歴史的に「良い買い場」となってきた一方、
今回はETF・機関マネー・高金利・規制といった新要因が重なっていることを踏まえ、
「過去と完全に同じにはならないかもしれない」という前提で臨むこと。
このあたりを押さえつつ、余剰資金の範囲で・長期視点で・冷静にビットコインと向き合うことが、シティの警告を「恐怖」ではなく「判断材料」として活かすポイントになります。