
2019年の日本の仮想通貨業界内ではさまざまな動きがありました。規制も以前より強まったなか、コインチェック株式会社では、モナコイン(MONA)の新規上場や、これまで日本で例の無かったステラ・ルーメン(XLM)の取り扱いを始めるなど、業界発展に向けて最前線で活動し続けています。
今回はコインチェック株式会社 執行役員である大塚雄介氏にこれまでのいきさつや今後の展望、そして「あの事件」の裏側などについてお聞きしました。
仮想通貨とコインチェックの今後
コインチョイス編集部(以下、編):まず、今後の日本の仮想通貨業界にとって、一般層への普及に必要なものは何だと思いますか?
大塚雄介氏(以下、大塚氏):一般の人々に届いていくのに、仕組みが難しすぎるIEOなどは多分まだ時間がかかるのではないでしょうか。IEOは、業界にいる人にとっては非常に画期的なことですが、一般の方々にそのような革新的なことは求められていないと思っています。簡単に送金できたり、気づいたらお金が増えていたりといった基本的なことを、何も考えずに行えるようになることが一番普及につながると考えています。
例えば、以前あったことなのですが、外国に留学したお子さんに仕送りするというときに、これまで郵便局で送金していたそうです。今までは郵便局に行き、1,000円の手数料をかけて送金していたものが、仮想通貨を利用すればスマホの操作だけで完結できますよね。こういったモデルケースがこれからも出てくれば、普及につながっていくでしょう。
他にも、債券や不動産のように、仮想通貨でも同様の仕組みがあってもいいかもしれません。超低金利時代と言われるなかで、銀行へ預金していても利子がもらえないということもあってか、比較的高金利とされる不動産クラウドファンディングなどが注目されています。ここでもらえる金利が、法定通貨でなく仮想通貨でというのもおもしろいかもしれません。仮想通貨を用いて、かつ分かりやすい方法で金利がもらえるといった仕組みがあれば、これも普及に繋がることになりますね。
編:コインチェックの展望や目指す姿などをお聞かせください。
大塚氏:私たちの目指すものは創業から変わっていません。まず、金融やITといった内容は一般の人には難しすぎますよね。私もこの会社に来た時には「指値(さしね)」が読めませんでした。金融は特殊な言葉を使いますが、一般の人でも「板を見る」とか言われても分からない人が多いのではないでしょうか。
私たちの務めは、「小学校のお子さんがいる母親」のような一般の人が仮想通貨を使えるようになるために、金融用語を覚える必要も、マニュアルを読む必要もなく、簡単に何も考えることなく利用できるアプリケーションやサービスを出していくことだと思っています。

編:2019年11月に経営体制の変更がありましたが、そのタイミングに関して何か理由はありますか?
大塚氏:変更が行われる前は、マネーロンダリング対策や内部体制の整備など業界全体が整備されるにつれて「やるべきこと」が増えてきており、自分たちでそのやるべきことをちゃんとやるというフェーズでした。それがひと段落し、私たちが創業の頃からある「やりたかったこと」をやっていくに当たって、マネックスグループも含めた全体で、次のフェーズに進もうという意思決定の下、経営体制が変更されたという形になります。
編:日本の仮想通貨業界は世界と比べて遅れている印象ですが、いかがでしょうか。
大塚氏:世界に比べると、日本は進んでいる国だと思います。資金決済法も元々はニューヨークのライセンスに次いで作られていますし、行政と業者の間での議論もきちんと行われています。事業者の立場から見ると、さまざまな規制があって大変ですが、業界の健全化に向けてやるべきだと思うことは大いにあります。
2017年はまだ市場規模が小さく、各企業がやりたいことにチャレンジできる時代でした。しかし、現在のように仮想通貨の市場規模が何十兆円という単位になってくると、社会を成り立たせるためにやらなきゃいけないことも数多く出てきています。今は、「やりたいこと」と「やらなければいけないこと」を両立させなければいけない普及期に入ってきています。日本はその風潮の中でも、先んじて「やらなければいけないこと」に、業界が進んだ国であると捉えています。
海外の方が発展が早いと感じてしまうのはカルチャーの問題もあります。3年ほど前にアメリカの公聴会で「ビットコインは公的にどのように扱われるべきか」と、既存の金融機関や仮想通貨事業者によって議論されたことがあります。
そのときの結論は「一旦容認して、様子を見よう」というものでした。脅威もチャンスもあるけれど、まだ規模も小さいから見守っていこうというアメリカのフロンティアというカルチャーがあったために、この結論に辿り着いたのでしょう。
国内の業界のフェーズも以前から非常に変わったと思っていて、我々が事業を始めた段階では新しいテクノロジーに対してチャレンジしていく段階でした。そこから、基準など地盤固めをする段階になり、業界全体が整備され、また再びチャレンジするフェーズに入るという段階です。今はその過渡期にいるように感じています。
編:レバレッジ規制強化(4倍から2倍への変更の可能性)、仮想通貨に関わる税金問題(政治献金税金補助問題)などが認知向上、利便性の足かせとなることはないのでしょうか?
大塚氏:政治献金の話は、現在の税制で読み解くと非課税だという結論になるのかもしれませんが。レバレッジの倍率についても、100倍での取引が可能だから進んでいるというわけではなく、それによって影響を受けるユーザーもいるので、利用者保護とのバランスを見る必要があり、その点を持って世界から遅れを取っているとは言い切れないと思っています。
規制強化の話題によって、日本は後進国になるんじゃないかと不安になるユーザーの気持ちも、もちろん分かります。どの程度の規制が適切なのかは事業者とユーザー、そして行政も含めて対話を重ねた方がいいとは思います。
対話をする上では、そもそもの現状の金商法や資金決済法、税制がなぜそのようになっているかも理解しなければいけません。その上で、今の時代に適しているのかどうかを考えていかなければなりません。仮想通貨は、これまでの概念とは全く異なるものなので、何も基準がない状態です。そのような中で様々なことを判断していかなければいけないのは非常に難しいですが、それでも4年ほど前に比べて、金融庁も我々もお互いの理解度は進んできています。
編:「お互いの理解度」とは、日本として海外にどのような姿勢でいるのかを見せていくということも含まれていますか?
大塚氏:そうですね。例えば、アメリカは州ごとに取り決めをしている中、ニューヨークだけは進んでいたり、中国は中央銀行の通貨発行をしようとしたりしています。こういった世界の情勢に対して、日本はどのような立ち位置にいるのかということを事業者も考えています。事業者にとっては、もちろん国内だけでなく海外にもビジネスチャンスがあるからですし、国としては諸外国の出方をみた方が良いのか、それとも先んじて動くべきかなどといった議論は繰り広げられています。
XLM上場や兄弟会社のSTO協会加入など新たな動きについて

編:先日よりステラ(XLM)の取扱が開始されましたが、金融庁の規制が強化されてから初の新しくホワイトリスト入りした通貨であると思います。どうして取扱うこととなったのか、経緯をお教えくださいますでしょうか?
大塚氏:新規通貨の上場については、流動性が高いなど、コインチェックの定める取扱基準を基に選定し、JVCEAへ申請しています。XLMは基準に適したものだったというだけの話で、XLMだけが特殊ということではありません。
ユーザーのなかには自分が保有しているコインの上場有無を気にして、TwitterのDMなどで連絡をくれるユーザーもいますが、そういった市場の声だけに影響されていることはなく、コインチェックとしての取扱基準をもって判断しています。
編:兄弟会社のマネックス証券もSTO協会に加入するなど、日本でもSTOが行われるような動きを感じられますが、その場合、証券のトークン化が必要になると思われます。この時、コインチェックが主導もしくは関係していくのですか?
大塚氏:兄弟会社ですので、お互いに情報を共有していきますが、マネックス証券が主体となって進めているものになります。協会自体も参加企業は全て証券会社ですし、証券に関わる法律の専門家内で話をした方が進めやすいでしょうね。
編:どのブロックチェーンを用いたらいいのかという相談や、独自チェーンの開発などに関する質問はありませんでしたか?
大塚氏:技術的な点に関する相談などはありますが、STOはそもそも「証券発行業務が高コストになっている部分を、いかに効率化できるか」という意味合いで行われるものだと思っています。そうなってくると、証券発行業務というものを知らなければ作れません。
そしてシステムを用いて効率化しようとなったときに初めて、ブロックチェーンなどの技術面の話になります。どのブロックチェーンにするかといった議論はもう少し先の話ですね。
「あの事件」を振り返って
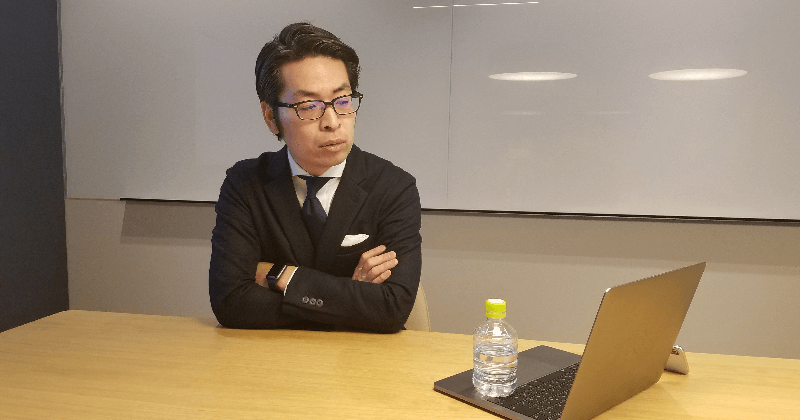
編:今振り返って、NEMのハッキング事件から学んだ経験や得られた考えなどはありますか?
大塚氏:2017年夏頃から、仮想通貨は本当に社会のインフラになってきたと強く感じていました。創業したばかりの頃は、社会レベルになるものではなく、単なる1つのWebサービス事業をやっているという感覚でしたが、規模が大きくなるにつれて、メディアも興味を持ちさらに社会への影響も大きくなっていきました。良くも悪くも、仮想通貨は期待と不安の入り混じった社会現象になってきて、既に「やりたいからやってる」だけでは進めない領域になっていたんですよね。
フェイスブックがケンブリッジ・アナリティカ事件で非難を浴びたのは、社会への影響力が非常に大きなプラットフォームになったからだと言われているように、新しいテクノロジーやサービスを社会に広く浸透させるには、世の中と折り合いをつけながら行っていかなければいけないと感じました。
ただ、それだけ仮想通貨市場が大きくなったということは、さらに発展の可能性の高い市場になったということでもありますし、やってきたことに意味があったと実感しました。
編:事件後にマネックスグループから提携のお話などがあったと思われますが、そのときの大塚さんの苦悩などはありますか?
大塚氏:色々ありますが、経営の立場としてユーザーと従業員を守ることが一番大切だという考えが私の中ではありました。あとは、今できる最善の選択肢を取ろうと考えました。
NEMの補償を行うという発表は事件から2日後に行いましたが、事件当日には自己資本によって補償する方針は決まっていました。あのときは会社もどうなるか分からないという状況でしたが、私の中では「もし終わるとしても終わり方がある」という思いがあり、その時は「もう出来ることをやるしかない」と覚悟は決まっていました。
編:記者会見のときはどのようなお気持ちでしたか?
大塚氏:もう「出るしかない」と思っていたので、変に緊張したりはしませんでした。このとき、会見のやり方を二つ提示されていたんですよ。一つ目は一時間で会見を終了し、質問もそこで受け付けないという、時間で区切ってしまうもの。二つ目は時間はエンドレスで、質問全部に答えるというもの。その時点では分かっていることや話せることは少なかったのですが、可能な限り説明しようと、後者と即答しました。
これからの仮想通貨に必要なこと

編:「イーサリアム2.0」やNEMの「Catapult」などの大型アップデートも控えており、ビットコインでも「コア0.19」がリリースされたなど、機能的な拡充が昨今では見受けられました。今後、仮想通貨にはどのような機能が重要視されると思われますか?理由と共にお聞かせください。
大塚氏:ビットコインにはビットコインの使い道があり、ネムにはネムの使い道があるように、通貨それぞれに目的は違います。
一般の人に普及していくことを考えれば、送金の仕組みを効率化する改善が必要になるでしょう。その方法として、コアのアップデートか、サイドチェーンを開発するのか、それとも取引所間でエスクロー方式を取るのかなど、改善策は数多くあります。その中でベストな手段を探していくことになるのではないでしょうか。
ただ、「送金が遅い」ということは既に事実としてあるので、改善されなければ、実需の中での使い方には制約が生まれ、普及にはつながらなくなってしまうのではないかと思いますね。
編:大塚さんが投稿されたnoteに「仮想通貨市場以上に伸びる市場は見つけられていません」とありましたが、その理由など具体的にお聞かせください。
大塚氏:マーケティングの分野から考えると、ビットコインのネットワーク効果はもう外れることができないくらい、普及してしまっています。ビットコインはほぼ基軸通貨となっていると言われています。
もしこの10年分のネットワーク効果を覆そうとするなら、ビットコインの10倍くらい進んだ技術が必要になるんじゃないかと、個人的には思っています。
仮想通貨は「価値の交換における共通規格のプラットフォーム」なので、ここから抜けるのは難しいでしょう。また、既にこれだけの規模の市場となっているにも関わらず、技術的にまだ黎明期であることから、さらに市場は成長し続けていくのではないかという期待もあります。そして送金が早くなれば、実需も加わってきます。これほど産業の変化を感じられることから、ブロックチェーンは50年に1度あるかどうかの技術であると思っています。
■コインチェック:https://coincheck.com/ja/
■関連:コインチェック口座開設方法を解説














